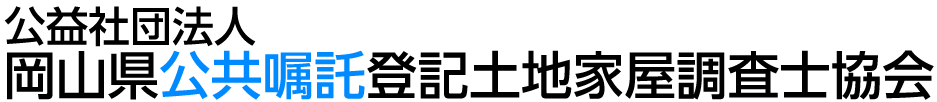お知らせ :新着情報
首相 所有者不明土地対策の総合的な対策を指示
安倍総理大臣は、経済財政諮問会議で、土地の持ち主がわからず放置されている「所有者不明土地」が、高齢化によって今後もさらに増えるおそれがあるとして、総合的な対策の作成を指示しました。政府は来月にも関係閣僚会議を設置し、土地の所有権や登記制度の在り方について検討を進める方針です。
総理大臣官邸で開かれた政府の経済財政諮問会議では、土地の相続の際に登記が更新されず、持ち主がわからなくなったまま放置されている「所有者不明土地」をめぐる対策などについて意見が交わされました。
この中で、石井国土交通大臣は、都道府県知事が一時的に所有者不明土地の利用権を設定できるようにすることや、市町村が持つ固定資産税の納税者情報を、ほかの行政機関が相続人を探すために使えるようにすることなどを盛り込んだ法案を、来年の通常国会に提出する方針を示しました。
これを受けて、安倍総理大臣は「高齢化の進展に伴って大量の相続が発生し、今後、所有者不明の土地がさらに拡大していくおそれがある」と指摘し、菅官房長官や石井大臣ら関係閣僚に対し、協力して総合的な対策を作成するよう指示しました。
政府は、来月にも菅官房長官を議長とする関係閣僚会議を設置し、土地の所有権や登記制度の在り方について検討を進め、来年のいわゆる「骨太の方針」に、抜本的な見直しに向けた論点を盛り込みたい考えです。
NHKニュースから
地球に電気帯びた粒子到達
太陽表面の爆発現象「フレア」が6日夜観測され、情報通信研究機構によると、太陽から放出された電気を帯びた大量の粒子が8日午前9時ごろから地球に到着し始めたという。人体への影響はないものの、過去には人工衛星の故障や大規模停電のほか、全地球測位システム(GPS)の誤差が大きくなるといったトラブルを起こした経緯があり、警戒を呼び掛けている。(毎日新聞)
国立研究開発法人情報通信研究機構のウェブサイト
https://www.nict.go.jp/press/2017/09/07-1.html
災害復旧における境界標識の保存について
平成28年熊本地震による被災地において,今後,がれきの除去や倒壊家屋等の撤去等の復旧作業が見込まれるところですが,復旧作業に際しては,土地にコンクリート杭,金属鋲などが埋設されていないかどうか注意するようお願いします。
これらは,土地の境界を示す「境界標」であるかもしれません。
境界標は,たとえ地震により位置がずれていたとしても土地の境界を特定するために役立つもので,紛争の予防・解決にも重要な役割を果たします。今後の被災地の復興のために,可能な限りその保存が図られるよう配慮をお願いします。
境界標識のほか,塀・石垣の基礎部分や側溝なども土地の境界を特定するために役立つものですので,可能な限りこれらの保存についても,留意されるようお願いします。
〔被災地の法務局の連絡先〕
熊本地方法務局不動産登記部門 電話 096-364-2145
音声ガイダンス番号〔境界標識について〕2→1→2
(平成28年4月21日 法務省HPから)
国土交通省「空家等対策の推進に関する特別関連情報」
●基本指針(概要)
東京と大阪、境界画定2割未満 法務局の土地地図整備
不動産登記法は、土地の区画を明確にし、それぞれに番号(地番)をつけた地図を法務局に備えると規定。これを「登記所備え付け地図」と呼び、市区町村が実施する地籍調査と法務局の調査などに基づいて作成される。大都市は法務局が担当することが多い。
(2015/5/4 東京新聞)