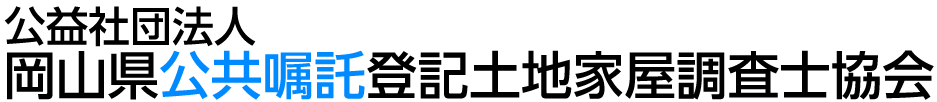お知らせ :新着情報
全国の地籍調査 進ちょくは約5割 都市部で進まず
(2014年06月25日)
国土交通省は6月24日、13年度末時点の全国の地籍調査の進ちょく率を取りまとめ、発表した。
それによると、全国の地籍調査の進ちょく率は51%。人口集中地区(DID)である都市部は23%、また、高齢化が進んでいる山村部(林地)は44%などとなっている。都市部は、土地が細分化され権利関係が複雑なため、思うように進んでいない現状だ。
地籍調査は、主に市町村が主体となって、土地の所有者、地番、地目を確認し、境界の位置と面積を測量する調査。全域調査完了となっている市町村は285、緊急地域(第6次国土調査事業十箇年計画において地籍調査を実施すべき地域とされているところ)の調査が完了しているのは、186市町村となっている。
それによると、全国の地籍調査の進ちょく率は51%。人口集中地区(DID)である都市部は23%、また、高齢化が進んでいる山村部(林地)は44%などとなっている。都市部は、土地が細分化され権利関係が複雑なため、思うように進んでいない現状だ。
地籍調査は、主に市町村が主体となって、土地の所有者、地番、地目を確認し、境界の位置と面積を測量する調査。全域調査完了となっている市町村は285、緊急地域(第6次国土調査事業十箇年計画において地籍調査を実施すべき地域とされているところ)の調査が完了しているのは、186市町村となっている。
(201/6/24 住宅新報社Web)
国土地理院「日本全国、3Dプリンタで立体模型に」
(2014年03月22日)
誰でも・簡単に・日本全国どこでも3次元で見ることができる「地理院地図3D」サイトを3月19日から公開
http://cyberjapandata.gsi.go.jp/3d/index.html
(2014/3/20 メール地図中心)
家屋の被害調査迅速に 災害備え市町職員ら研修
(2013年12月26日)
災害時の被災者支援や復興推進に必要な家屋被害の調査方法を市町職員らが学ぶ研修会が24日、松山市役所で始まった。26日まで、愛媛県内15市町の職員と土地家屋調査士の計約250人が順次受講し、講義や演習を通じ全壊や半壊といった損害の程度を迅速・的確に判定する手法の習得を目指す。
主催した松山市などによると、家屋の被害調査は、被害者が仮設住宅の入居や損害保険金支払いなどを申請するのに必要な罹災(りさい)証明書の発行に必要な資料となる。東日本大震災では罹災証明が法制化されておらず、被害調査方法も自治体間でばらつきがあり、発行が大幅に遅れる事例があった。
(12月25日 愛媛新聞)
主催した松山市などによると、家屋の被害調査は、被害者が仮設住宅の入居や損害保険金支払いなどを申請するのに必要な罹災(りさい)証明書の発行に必要な資料となる。東日本大震災では罹災証明が法制化されておらず、被害調査方法も自治体間でばらつきがあり、発行が大幅に遅れる事例があった。
(12月25日 愛媛新聞)
自由研究が本になった! じめんのボタンのナゾ
(2013年12月18日)
富山市蜷川小学校4年の本吉凜菜(りんな)さんが「街区基準点」について調べた自由研究が、本になって発行された。街区基準点は地面に打たれた金属びょうで、測量などの基礎となる。管理する日本土地家屋調査士会連合会(東京)が本吉さんの研究に注目し、より広く知ってもらおうと出版した。本吉さんは「自分のやったことが本になるなんて」と驚いている。
自由研究は2年生の夏休みに取り組んだ。通学路の地面に打たれた金属のびょうやプレートを「地面のボタン」と呼び、県土地家屋調査士会などを訪れ、土地の境界や街区基準点であることを調べて自由研究にまとめた。研究はその年の「全国小・中学生作品コンクール」生活科部門で最高賞に選ばれた。
日本土地家屋調査士会連合会では、本吉さんの自由研究を高く評価。基準点の意義を子どもたちに知ってもらうきっかけにしようと、昨年9月、本吉さんの文章や写真をそのまま印刷した絵本をつくり、全国の土地家屋調査士会に配布した。
同連合会はことし、さらに専門知識や写真を加えた子ども向け書籍「調べてみよう地面のボタンのなぞ 一番えらいボタンをさがせ」を編集し、日本加除出版(東京)から発行した。B5判36ページで、基準点の目的や種類を分かりやすく紹介している。
本吉さんはこの夏、月の動きや形を観察した自由研究「お月さま またあした」でも全国小・中学生作品コンクール理科部門で中央出版社長賞に選ばれ、一昨年、昨年に続き3年連続の入賞を果たした。自分の自由研究が本になり、「土地家屋調査士の人たちに喜んでもらえたので、やったかいがありました」と話している。
(2013/12/11 北日本新聞)
自由研究は2年生の夏休みに取り組んだ。通学路の地面に打たれた金属のびょうやプレートを「地面のボタン」と呼び、県土地家屋調査士会などを訪れ、土地の境界や街区基準点であることを調べて自由研究にまとめた。研究はその年の「全国小・中学生作品コンクール」生活科部門で最高賞に選ばれた。
日本土地家屋調査士会連合会では、本吉さんの自由研究を高く評価。基準点の意義を子どもたちに知ってもらうきっかけにしようと、昨年9月、本吉さんの文章や写真をそのまま印刷した絵本をつくり、全国の土地家屋調査士会に配布した。
同連合会はことし、さらに専門知識や写真を加えた子ども向け書籍「調べてみよう地面のボタンのなぞ 一番えらいボタンをさがせ」を編集し、日本加除出版(東京)から発行した。B5判36ページで、基準点の目的や種類を分かりやすく紹介している。
本吉さんはこの夏、月の動きや形を観察した自由研究「お月さま またあした」でも全国小・中学生作品コンクール理科部門で中央出版社長賞に選ばれ、一昨年、昨年に続き3年連続の入賞を果たした。自分の自由研究が本になり、「土地家屋調査士の人たちに喜んでもらえたので、やったかいがありました」と話している。
福島県公嘱協会が県民無料公開講座を開催
(2013年11月09日)
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は25日午後1時40分から、福島県郡山市の郡山ユラックス熱海で県民無料公開講座を開く。来場者を募っている。
復興庁福島復興局の中村伸也次長が「東日本大震災復興政策について」、早稲田大大学院法務研究科の山野目章夫教授(福島市出身)が「東日本大震災が与えた宿題-相続や建物の諸問題」をテーマに講話する。
入場無料。問い合わせは同協会 電話024(525)1055へ。
同協会は1日付で社団法人から公益社団法人に移行した。斎藤潔理事長は公開講座のPRと公益社団法人移行のあいさつのため6日、福島民報社を訪れ、高橋雅行社長と懇談した。舟山幸雄、渡部永継の両副理事長、柴山武専務理事が一緒に訪れた。
(2013/11/9 福島民報)
復興庁福島復興局の中村伸也次長が「東日本大震災復興政策について」、早稲田大大学院法務研究科の山野目章夫教授(福島市出身)が「東日本大震災が与えた宿題-相続や建物の諸問題」をテーマに講話する。
入場無料。問い合わせは同協会 電話024(525)1055へ。
同協会は1日付で社団法人から公益社団法人に移行した。斎藤潔理事長は公開講座のPRと公益社団法人移行のあいさつのため6日、福島民報社を訪れ、高橋雅行社長と懇談した。舟山幸雄、渡部永継の両副理事長、柴山武専務理事が一緒に訪れた。
(2013/11/9 福島民報)